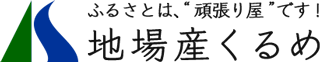福岡県知事指定特産民工芸品
籃胎漆器(らんたいしっき)
籃胎とは「竹かごを胎(はら)む(素地とする)」ことを意味します。その名のとおり、竹で編んだ器に漆をかけ、幾重にも研ぎだして装飾加工を施し仕上げます。京都の名高い塗物師・勝月半兵衛を久留米藩に招いてつくった堅地(かたじ)塗の伝統を基礎とし、明治20年頃、茶人の豊福勝次、竹細工師の近藤幸七、塗師の川崎峰次郎の3人が力を合わせて造り出したものだといわれます。姿の美しさだけではなく、軽く丈夫で、使うほどに味わいを増すことから、長い年月にわたり日常に用いる器として愛用されています。

城島鬼瓦(じょうじまおにがわら)
城島の瓦づくりは、関ヶ原の戦い後、久留米藩主として入城した有馬氏により始まります。優美な光沢と格調高い姿形・耐久性には定評があり、九州各地の神社や仏閣・日本家屋などに使われ、知られるようになりました。屋根の端を飾る「鬼瓦」は、厳しい形相の鬼の顔はもちろん、雲や菊など、様々な形状を模した魔除けとして一家を守ります。

久留米おきあげ(くるめおきあげ)
おきあげとは鮮やかな布などに綿を入れ、ひとつひとつ重ねて作る「押し絵」のことです。特に羽子板や壁かけに見られる華やかな雛や歌舞伎役者などが代表的なものです。由来は諸説ありますが、有馬藩の参勤交代の際に土産として文化が持ち込まれたのではと言われています。明治、大正時代まで筑後一円で盛んに作られ、顔を描く「面目(めんもく)師」など専門の職人がいましたが、現在は主婦たちによってその製法が引き継がれています。

筑後和傘(ちくごわがさ)
「筑後和傘」は、複雑な100以上の工程からなる細工が施された美しさと実用性を兼ね備える工芸品です。17世紀初めに地元の日吉神社の神官が副業したことが発祥とされ、柄や傘骨の材料となる真竹が筑後川経由で入手できたこと、和紙や柿渋の名産地が近かったこと、技術を持つ職人が多かったことなどを背景に、和傘の一大生産地となりました。昭和20年ごろ、町内に500人いたとされる職人も今は途絶え、地元・城島の伝統を残そうと発足した保存会により、技術が継承されています。

八女手漉和紙(やめてすきわし)
「八女手漉和紙」の起源は、九州で最も古く、400年以上前越前の僧・日限上人が、矢部川の地理や水質製紙に適しているのを見て、加工術を伝授したと言われます。大きな特徴は、この地方特有の長い繊維の楮(こうぞ)を用いるために、他産地にはない強靭な和紙ができること。繊維が太く腰が強く、耐久性に富んでおり、掛軸、障子紙、ふすまの内張りなどの表装用の和紙として高い評価を受けています。

掛川(かけがわ)
仏前用の敷物として使われる「掛川」は、い草の産地として知られる筑後一帯で古くから生産されてきました。い草特有の爽やかな香りと鮮やかな色彩には風格があり、織り目が詰まった独特の肌触りが人気です。掛川は、い草農業が多かった40年ほど前まで、大木町で生活している女性の内職として盛んに織られていましたが、今でも、筑後の夏の風物詩的な存在として、多くの家庭で愛用されています。
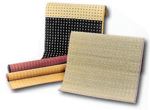
八女石灯ろう(やめいしとうろう)
「八女石灯ろう」の特徴は、地元から多く産出される凝灰岩にあります。凝灰岩には、軽くて柔らかく風化しやすい石材で、細かい細工に向かない反面、寒さや熱に強く石苔を早くつけやすいなど、庭灯ろうに最も適した石質を持っています。江戸時代、この地域では石橋づくりなど多くの石工が活躍し、それに伴って石灯ろうの生産も盛んになりました。

八女和ごま(やめわごま)
「八女和ごま」の起源は、菅原道真公が伝えたというものなど諸説があります。上面の中央部分にある大きなくぼんだ「ヘソ」が特徴で、これは明治時代以前の形状からの名残りではないかと言われています。こま作りには、樹齢30年以上のまっすぐ伸びた木を、約1年を費やして乾燥させるなど、長期間の工程が必要です。
また、こまを長く、勢いよく回すたには、木の芯がこまの中心になっていることが大切であり、熱練の技が要求されます。
八女竹細工(やめたけざいく)
八女地方は、赤土の粘土性が高く、良質の真竹と孟宗(もうそう)竹に恵まれています。それらの竹を材料に作られる「八女竹細工」は、宝永年間(約300年前)に福岡藩と高鍋藩から技法が伝わり、やがてその技法がひとつに合わさって有馬藩の下級武士の副業として始まりました。特に縁巻の仕上げの丁寧さが特徴で、巻きヒゴは一気に10m前後の薄いヒゴを作り、籠の縁にしっかり巻き付けます。染料も接着剤も使わないにもかかわらず、耐久性に優れ、5,60年は実用品として使用できる逸品です。

大川総桐箪笥
桐は、調温や保湿効果・難燃性に加え、防虫効果もある高温多湿な日本の風土に合った木材です。「大川総桐箪笥」は、そんな桐の特性を最大限に活かした、木目の美しさが魅力の家具で、最上の柾目の厚板を用いた、緻密な職人技で作られています。引き出しの奥には、空気の抜け穴となるカラクリもあるなど、緻密さゆえの開け閉めの感触や桐が持つ肌触りの良さも好まれています。

大川彫刻(おおかわちょうこく)
「大川彫刻」は、薄物の屋久杉の板を使い、木目の繊細な線の美しさを生かすことで立体感を出す伝統の透かし彫りです。木を見極める職人の感性と、日々鍛錬を重ねた技術に裏付けされた逸品です。その技術は立花藩の立川流の流れを組み、江戸末期には神社仏閣の装飾品が多く作られました。昭和に入るころにその高い技術は一般化し、日本家屋の実用性と装飾性を兼ねた様式として重宝されています。
大川組子(おおかわくみこ)
「おおかわくみこ」は、約300年の歴史を誇る美しさと緻密さを兼ね備えた工芸品です。三組手(みつぐて)と呼ばれる三角形の地組みの中に、200以上とされる図柄の組木を組み上げる技術には、数ミクロン単位を調整できる職人の勘が必要だといわれます。多い時は、数万個の部品により組み上げられますが、見た目は華奢でも、それぞれの部材が精巧に噛み合い、一枚の板のような頑丈さとなります。
鍋島緞通)なべしまだんつう)
「鍋島緞通」は、元禄年間(約300年前)に古賀精右衛門が、中国からの技術を習得し「扇町(おうぎまち)毛氈(もうせん)」として織ったのがはじまりで、これが日本最古の綿緞通といわれています。
海外の緞通が羊毛製であるのに対し、当時地元で多く採れていた木綿糸を使っていることが大きな特徴で、高温多湿な日本の気候にふさわしい敷物として、その肌触りや使い込むほどに味わいを増す品質が多くの人々に愛されています。